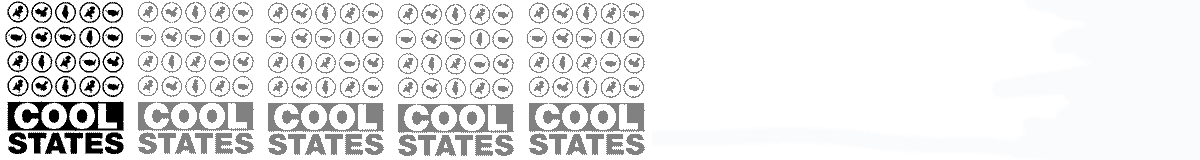April 10, 2003
映画コンテンツの「産地直送」で産業としてのインディースの可能性を拓く
境真良経済産業省メディアコンテンツ課課課長補佐(1)
- cool states
- 10:51 PM
- Category: B: Cool States Communications |
- Category: 政治経済
ここ数年、日本における映画興行収入が過去最高の数を記録する好況の裏で、その牽引役になるのはほとんどハリウッドからの洋画とジャパニメーションという状況を呈している。映画を作らないことが映画会社にとって成功するビジネスとまで言われるままに、日本映画は勢いを失いつつあるのだ。もはやハリウッドどころかややもすれば海外からのインディースフィルムにまで客足を取られてしまうまでに落ち込んだこの状態は、映画館にも影を落とし、好況の裏腹で郊外や地方を中心に既存の映画館の客足は鈍る一方、シネマコンプレックスに今まで映画館に足を運ばなかった人々まで押し寄せるような現象が起こっている。
デジタルがつく前に、映画というコンテンツの世界は、ユーザー主導の構造変革の真っ只中にあるのである。
その中で、コンテンツの王様である映画が強くならなければ、国際的な競争の真っ只中で日本のコンテンツの将来そのものが危惧し、転換に向けて取り組む一人の官僚がいる。
インディースのための新たな映画コンテンツのビジネス回路を開く
3月18日、デジタルコンテンツの産業振興の支援を目的に経済産業省が中心に毎年開催しているデジタルコンテンツジャパンというイベントの会場である東京北青山のTEPIAで一風変わったミーティングが行われた。自身が取り組んでいる映画を公開したいプロフェッショナルやNPOたちと、映画を上映したい地域の人々が、お互いを紹介しあう交流会形式のパーティー「映画 de しゃべり場」である。その歓談の中心で一際明るい声を発して場を盛り上げる一人の人物がいる。この人こそ、コンテンツとしての日本映画の振興のための実験的な取り組みとして、映画館だけにとどまらない地域コミュニティーで上映ビジネスのモデルを作ってみようと、この「場」のもとである「デジタルコンテンツ地域上映事業実証試験(愛称:デジタル de <みんなのムービー>プロジェクト)」を編み出した境真良経済産業省メディアコンテンツ課(文化情報関連産業課)課長補佐である。
ところでなぜ、映画館以外で映画を上映することが特別なことなのであろうか。今まで配給会社が映画を興行会社(映画館)に卸すことで、全国規模の配給網が決定し、内容よりもシステムとして安定供給がされて来た伝統的な経緯があった。そのため、このネットワークを守るため、メジャーな映画が映画館を介さずして配給網に乗ることはありえず、逆にいえば配給会社にかからない映画はネットワーク外でしか上映できない状態が続いてきたのである。すなわち、映画館以外で上映する映画は、既にメジャーではない映画だけなのであった。
このような映画コンテンツの流通を取り巻く特異性が、日本映画において少数の映画会社だけでしかメジャーなコンテンツを作り出し、供給することが出来ないという集中を招いていると境氏は指摘する。そのことが新しい才能を競争させるチャンスすら奪っており、そのことが日本映画を弱くしていると危惧している。
今や硬直化した映画コンテンツ制作と流通のシステムに向けて、オルタナティブになるようなシステムを提案することで、一つのブレークスルーを試みたのが「デジタル de <みんなのムービー>プロジェクト」である。
公共ホールでありながらクオリティーの高い映像コンテンツの公開をデジタルの力で実現
テレビやゲーム、ブロードバンドなど、コンテンツの形態が広がる中にあって、メディアの王様である映画の制作を志し、取り組んでいる人々は今も数え切れないほど存在する。その中の一人の取り組みがこのオルタナティブな興行の姿の第一歩を記すことになった。
音楽プロデューサーとして有名なつんく氏も映画制作に思いを寄せていた一人である。その思いから、映画はどのように作られ流通するのか、その現実の一部始終と新しい映画作りの可能性を、視聴者に公開しながら実際に起動させようというテレビ番組「つんくタウン」をフジテレビで平成十二、三年度の二年間にわたり作り出した。
どの配給会社の手も借りずに自力のプロジェクトで作り出した映画を自身で上映したい。既存の映画界にない多彩な顔ぶれによる監督作品の映画が、この番組上でインディースをメジャーかさせるために、米国などで今まで用いられてきた、様々な手法を使ってプロデュースされて行った。この思いが境氏のビジョンと合致、映画の配給ではなく、地域コミュニティーと結びついたコンテンツ流通の実験という名目で動き始めたのである。実験のためのコンテンツは、あえて上映方法を未定にしていた、モーニング娘。出演による映画だった。
結果、「つんくタウン」に登場した境氏、プロデューサーつんく氏とのテレビでの公開打ち合わせ。これに呼応したのが松下電器の加計晃氏であった。松下はデジタルシネマ上映用のビジネスモデル(現在はP-ddという会社になっている、加計氏は同社代表取締役
URL http://www.p-dd.co.jp/)を開発、この映画館のような特別な技量を上映に必要とする特別な空間に備え付けるような設備でないと大規模な上映が行えなかったフィルムの世界から、どこでも持ち込んで簡単に上映できるデジタルの技術の実現を広く認知させようと企図していた。ここでどこでも高品質で上映できるシステムの存在が明らかになる一方、地域でコンテンツを見せたいという声が全国青年会議所からあがっているという情報が寄せられる。ここで地域コミュニティーによる新しいコンテンツ流通をテーマにした経済産業省による実験が開始されることになったのである。
各地の青年会議所、NPO等が公共ホールを確保し、つんくタウンムービーが各上映地に映画を提供、そこに松下が機材を提供する。映画の売り上げは各主催者がつんくタウン側に直接支払いする一方、上映機材については松下が提供した機材をコンテンツ流通支援として経産省の予算で調達し、それを輸送費のみで上映者に提供するスキームで行われた。このプロジェクトで映画上映に関する情報を得られる経産省が投入した費用は七百万円。それに対して実際のプロジェクトとして新たに動いた額は一億円近くにものぼり、一つのモチベーションの提供がささやかながら新たな動きを巻き起こしたのである。
映画コンテンツの「産地直送」が始まった
そして、昨年度である平成十四年度、つんくタウンのように映画を自立して制作しているプロダクションと、地域コミュニティーの中でコンテンツの上映を行いたいと希望する受け皿との間をマッチングするマーケットプレイスとして、「デジタル de <みんなのムービー>プロジェクト」が始まった。つんくタウン時代からの違いは、デジタルコンテンツの振興を業務とする財団法人DCAjに事務局を置き、無料登録のマッチングの場を 協議会として作り出したことである。この協議会の調整のもと、マッチングが成功し、契約を交わした上映側に機材費無料の実費でデジタル上映用機材を貸与するシステムになっている。
「既存の流通網に乗っかって、配給されたものをそのまま上映してしまうような多くの映画館のしくみにはコストとマーケティングというビジネスに必要不可欠な意識が存在していなかった。そのことが映画館の斜陽を生み出している」と指摘する境氏、「これらのビジネス意識がはっきりしているシネコンにこれでは太刀打ちできないのは当たり前である」と語る。「ところが『デジタル de <みんなのムービー>プロジェクト』のようにデジタル技術を応用した上映手段によって設備そのものを持たなくても良くなった、ここで本当にコンテンツの内容そのもので成否を反映できる機会を作り出すことが、最初のかたちではあるが出来た」と評価する。「しかし、今までの映画のシステムの閉鎖性から、配給する側も上映する側も商慣習に慣れておらず、契約の方法から取り分の調整の仕方まで一から経験しなければならない」とビジネスともいえない初歩的な状況を認識、事務局はビジネスとして成り立たせて行くためのサポート役の機能も担いつつあるという。
この記事は映像新聞に寄稿したものです