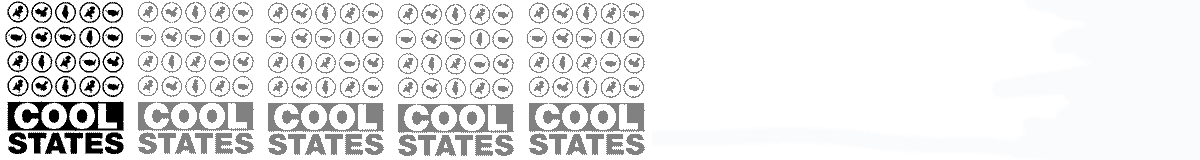April 22, 2003
境真良経済産業省メディアコンテンツ課課長補佐 (2)
- cool states
- 10:54 PM
- Category: B: Cool States Communications |
- Category: 政治経済
映画コンテンツの「産地直送」で産業としてのインディースの可能性を拓く
より続き
デジタルシネマに上映技術が進化する映画。その進化はフィルムをかけるという装置の束縛を開放し、それを導入した映画館なみの大画面の高精細映像を地域のホールや公民館でかけられる、いわば、どこでもシネマの可能性を持っている。
この可能性から既存の硬直した日本の映画産業システムのパラライムを変える一穴をつくり出そうとしている経済産業省メディアコンテンツ課課長補佐の境真良氏。境氏が編み出したその一穴とは、デジタルシネマ上映のシステムをコンテンツの上映を通じて地域を盛り上げようとする団体やNPOに一日単位で無料でレンタルする一方、これら上映を求める人々と新たな映像の担い手が持つ映画コンテンツをマッチングして、今までに無いかたちの映画コンテンツの市場を作り出そうというもの。
そのコンセプトがそのままタイトルにあらわれた「デジタル de <みんなのムービー>プロジェクト」が現実の政策として編み上げるまでの話を前編で触れたが、後編では<みんなのムービー>の次にある一手に向けた境氏から発せられるビジョンをお届けしよう。
「デジタル de <みんなのムービー>プロジェクト」の一穴が何をもたらすのか。このプロジェクトが映像コンテンツを求めている地域の潜在的な需要を顕在化することになるであろうと境氏は期待している。
日本中に無数に存在する公共ホールや公民館、その立派な箱物に比べて、地域の需要にあって妥当なコストで公開できるコンテンツの不足が深刻化している。また、住民参加で文化をつくり出すまちづくりの機運が日常的なものとして起こり始めている中で、このようなユーザーの任意性の高い映像コンテンツのマーケットが生まれることは、これら本来、映像コンテンツの上映をコミュニティービジネスとして必要としている存在に市場を開くことになると考えられる。演劇や音楽、芸能の他にある映像時代だからこその、有力な新たなコンテンツがライブとは異なる新たなコスト感覚で、そして映画祭など特別なことをしなくてもやっと使いこなせる環境を手にすることになるのである。
一方で、映像の送り手側にとっても、情報を直接市場に提供することでより多くの上映チャンスを獲得することが期待できる。このマーケットにある情報は、地域上映のためだけでなく、コンテンツとしての取引を求める立場にとってもアクセスできる、インディーズのためのマーケットプレイスの機能も同時に果たせる潜在力を持っているのだ。
ここでやり取りされ、上映されるものは実は既存のシステムでいうところの映画ではないのが肝である。確かにこれは映画なのだが映画ではなく、コンテンツである。映画が映画である以上、今までの伝統的な配給システムや映画館業界の中に組み入れられてしまうため、先に触れたように映画祭など特例的な扱いや、はなっから配給システムから外されている例えば平和映画など啓蒙性のある映画や旧作などしか自由に映画館外ではかけられなかったのが現実であり、その縛りは地方に行くほど多かったのである。
「ほとんどの映画館は今まで配給から流れて来る映画をかけているだけで、映画館として生き残るためにコンテンツをかけるというビジネス感覚がどれだけあったかは個人的には疑問を感じている」と境氏は語る。「売れるコンテンツを自身で選んで入手し、上映するという、マーケティング意識が根付かないところは淘汰されて行くだろう。実際、シネコンはそれをシビアに実践しているから客が集まるビジネスモデルになっているのだから、太刀打ちできないのは当然のこと」であると指摘する。確かにシネコンの存在が邦画洋画を問わず、メジャーな配給系ではない映画のブームを全国規模に高めた起爆剤のように見受けられる。既存の映画業界がコンテンツニーズの膨張の中で埋めきれない存在になっている中で、それを果敢に埋めるであろう新たなコンテンツの担い手であるインディーズがレベルを高め、メジャー化して行ける成長の舞台もまた、既存の映画上映の外にある新たなスキームを多様なものにすることにかかっているのである。その中の流れに、ミニシアター、シネコン、そして<みんなのムービー>が投じられたのである。まさに「どこでも」映画というコンテンツが入り込める環境を見えるかたちで提起しようとしているのである。
<みんなのムービー>には、地域上映にとどまらない提起力を持ったしくみが既に内包されており、これこそが次のビジョンを垣間見せる。上映を求める者とコンテンツを提供したい者がマッチングするする材料になるのは、WEB上それぞれが自己公開するコンテンツや上映条件等の情報データである。これは<みんなのムービー>にとどまらない、配給やバイヤーとフィルムメーカーを結ぶ、インディーズのための新たなマーケットプレイスにもそのまま転用可能なものにも見受けられる。インディーズがメジャーに向けて成長できる、もしくはコンテンツビジネスとして展開できる、オープンな市場作り向けた布石を既に境氏はビジョンとして考え始め、打っているのである。
「メジャーとインディーズはどちらも無くてはならない映像の生態系の中で補完関係にある二つの要素。インディーズが無ければメジャーに対する才能供給が限られたものになってしまう。メジャーを目指せなければ、映像の世界に飛び込む才能すら枯れてしまう。この事業を通じて、メジャーの人に、自分の会社が日本映画を支えるという自負は大切だが、それを超えて日本映画界全体として長く繁栄できるビジネスのあり方、製作と配給、メジャーとインディーズの賢い関係のあり方をもっと考えてもらえたら幸せ」と境氏は語る。
映画コンテンツ産業の改革は国内にとどまらない。境氏のビジョンは既に海外に向いている。「欧米でもアジアでも日本のコンテンツ、特に映画やアニメなどの映像コンテンツに対する欲求が需要として考えられるくらい存在する。中国や韓国で海賊板のDVDなどで日本のコンテンツが広く取引されていることがそれを物語っている」と語る境氏には、この海賊版を求めてまで日本のコンテンツに触れようとする東アジアの人々や、様々なかたちで関心を示し既に映画「リング」のようなドラマから戦隊ものまで幅広いストーリーのリメークによる知的所有権販売、 ジャパニメーションのライセンシングなどで市場が見え始めてきた欧米のトレンドに、有望な輸出産業としてそう遠くは無い可能性が見えているのだ。実際に今年度より、ジェトロがアジアでは海賊版コンテンツから市場への変換、欧米では販路開拓支援を見据えた、コンテンツ輸出のための環境整備の取り組みを始めている。世界規模で流通する魅力ある映像コンテンツを常に潤沢に送り出し、産業として映画を再生するためにも、既存の硬直した映画産業のシステムではないコンテンツ産業としての構造転換にやはり行き着くのである。
この整備された市場とは決して言えなかった映画ビジネス。それは同様に放送ビジネスにもあてはまるだろう。これら様々な映像ビジネスがコンテンツ産業として一つの生態系を形成することが確かな流れの中で、誰もがメジャーに向けてチャレンジできる市場を整備する。その当たり前のことこそが、境氏のビジョンの中心であり、それを実現することこそがこの映像の新世紀で日本の映像産業そして文化が生き残る道であるということだと提起しているのである。